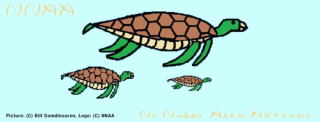原賠法とはdetail
損害の賠償に関する法律(原賠法)について
1.原賠法の目的
原賠法の目的は、原子炉の運転等によって原子力損害が生じた場合における損害賠償制度を定めることで、被害者保護と原子力事業の発達に資することとあります。(原賠法1条)。
2.原子力損害
「原子力損害」とは、核燃料物質の原子核分裂の過程の作用又は核燃料物質等の放射線の作用若しくは毒性的作用(これらを摂取し、又は吸入することにより人体に中毒及びその続発症を及ぼすものをいう。)により生じた損害をいいます(原賠法2条2項)。
一般的には、原発事故と社会通念上相当と認められる範囲で因果関係が認められる損害が賠償の対象とされます。具体的には、生命・身体への損害だけでなく、精神的損害、避難費用、農作物の出荷制限や風評被害による営業損害なども含まれます。原子力損害賠償紛争審査会が提示する指針をご参照下さい。
3.原子力事業者の無過失責任
東電などの原子力事業者は、原子力損害を発生させたときは、損害の発生につき故意・過失があったか否かに関わりなく、賠償責任を負います(無過失責任、原賠法3条1項本文)。民法上は、不法行為一般について、被害者が加害者に損害賠償請求するためには、被害者が加害者の故意又は過失を立証する必要があるので、原賠法は、原子力事業者の無過失責任を定めることで、被害者保護を図ろうとしているといえます。諸外国の原子力損害賠償制度においても同様に、無過失責任とするのが通例です。
4.原子力事業者に対する免責
「異常に巨大な天変地異又は社会的動乱によって生じた損害」については、原子力事業者に賠償責任がないとされています(原賠法3条1項但書)。このように原子力事業者が免責される場合、国が被災者の救助及び被害拡大防止のため必要な措置を講じます(原賠法17条)。
なお、11年5月13日、原子力発電所事故経済被害対応チーム関係閣僚会合において、東電の免責はないと決定しています。この主要な理由は、「異常に巨大な天災地変」とは、一般的には歴史上例の見られない大地震、大噴火、大風水災等が想定されており、今回の地震や津波は、歴史上例の見られない災害とまではいえないこと、原賠法3条1項但書で「異常に巨大な天変地異」と並記されている、戦争などの「社会的動乱」と同程度とはいえないこと、必ずしも地震により引き起こされたものとはいえないこと、また、地震時の全電源喪失は本件事故前から指摘されていたことなどがあげられます。
5.原子力事業者に対する責任集中
原子力事業者以外の者、たとえば、原子力事業者に原子炉など各種機器を提供しているメーカーなどは、原子力損害を賠償する責任を負いません(原賠法4条1項)。また、原賠法4条3項では、製造物責任法なども適用されないと規定されていろので、原子力事業者以外の者が製造物責任法に基づく賠償責任を負うこともありません。このように、原子力損害の賠償責任は原子力事業者に集中しています。その趣旨は、上記原子力事業者以外の原子力関連事業者の保護のほかに、被害者が容易に賠償責任の相手方を知ることができる、つまり、原子力損害については、原子力事業者に対して請求すれば賠償してもらえる、というように簡単に理解できることをもって、被害者保護を図る点にあるとされています。
しかしながら、原子炉メーカーが製造物責任法の適用除外を受けている真の理由は、日本がアメリカから原子力関連技術の供与を受け、原子力発電事業を始める際にアメリカから提示された条件のひとつだったからと考えられます。アメリカの原子炉メーカーとしては、原子炉設備の瑕疵による事故が万一起これば巨額の賠償責任を負うことになりかねず、そのようなリスクを負うことはできないというビジネス判断をしたのが実態です。
このためアメリカの技術をもとにして原子力発電を始めた国々は、原子力事故の民事責任についてはほぼ同一の法制となっており、それらの国の間では原子炉メーカーの製造物責任は問わないというルールが国際標準となっています。
原子力事業者への「責任集中」に真っ向から立ち向かっているのがインドです。インドには世界最大の化学工場事故という、歴史的な背景があります。1984年、インドのマディア・プラデシュ(中央州の意)の州都ボパールで米ユニオン・カーバイト社工場から漏れ出した化学物質イソシアン酸メチルにより一夜にして2000人以上が死亡し、その後さまざまな要因で1万5千人から2万5千人が亡くなったとされています。現在も周辺住人への健康被害は続いており、負傷者も含め、正確な数字は把握されていない状況です。そして、ユニオン・カーバイト社への訴訟や責任問題は未解決なのです。
そんな背景もあって、インドは原発の輸入に際しては輸出国、また製造メーカーへの訴追権を主張しています。輸出国との交渉では、これを条件としています。
6.原子力事業者の損害賠償措置、国の援助
原子力事業者は、損害賠償責任が発生する事態への備え(損害賠償措置)を講じることが義務づけられています(原賠法7条1項)。この損害賠償措置とは、原子力損害賠償責任保険契約(民間保険契約)及び原子力損害賠償補償契約(政府補償契約)を締結することです。この損害賠償措置として必要とされる額は、原則として、1事業所当たり1、200億円とされていますので、通常の原子力損害を賠償する場合には、民間の損害保険会社により、賠償措置額(1、200億円)まで保険金が支払われることになります。そして、民間保険会社による保険では対応できない原子力損害、たとえば、地震、噴火、津波などの自然災害による原子力損害を賠償する場合には、原子力事業者と政府との間の補償契約により行われる政府補償により、賠償措置額(1、200億円)まで補償金が支払われることになります。
また、被害者救済に遺漏がないようにするため、賠償措置額(1、200億円)を超える原子力損害が発生した場合には、国が原子力事業者に必要な援助を行うことができます(原賠法16条)。この国による必要な援助とは、補助金の交付や低利融資等が考えられます。